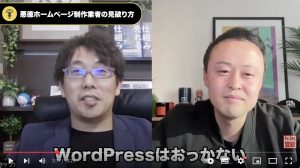ホームページ制作は本当に必要?SNS全盛時代に見直すべき理由/株式会社KACHI 取締役 久野⾼司
SNSやYouTubeが全盛の今、「ホームページ制作に投資する意味はあるのか?」という疑問を持つ経営者は少なくありません。
実際、業種によってはホームページがほとんど意味を持たないケースもあれば、逆に必須の武器となる場合もあります。
かつてホームページは、会社案内や事業紹介といった「Web上の名刺」としての役割が中心で、作れば自然と一定のアクセスが集まり、集客につながる時代もありました。
しかし今では、ホームページは膨大に増え、単に作っただけでは見られない時代になっています。
アクセスを集めるためには、検索エンジン対策(SEO)やSNS発信、広告運用など、継続的な集客施策が欠かせません。
つまり、ホームページの価値は「作ること」ではなく、「どう活用するか」に移っているのです。
ホームページが必要な業種・不要な業種
すべての業種にホームページが必須というわけではありません。
例えば、牛丼チェーンやスイーツ専門店、生体院など、すでにお客様が商品や価値を十分理解している業種は、SNSや口コミだけで集客が成り立つこともあります。
逆に、まだ価値が認知されていない商品や、複数の商品を扱う業種、高価格帯のサービスを提供する業種は、ホームページがないと信用を得にくく、詳細な情報を伝えられません。
また、法人間取引(BtoB)では、ホームページの有無が取引先選定の基準になる場合も多く、Facebookページだけで事業を運営するのは大きな機会損失になりかねません。
重要なのは「自社の業種・ビジネスモデルにおいて、ホームページが集客・営業プロセスのどこで役立つか」を明確にすることです。
ホームページ単体では機能しない理由
多くの企業が誤解しているのは、「ホームページを作れば集客できる」という過剰な期待です。実際には、ホームページは集客のプロセスの中の一つの歯車に過ぎません。
SNSや広告、展示会、紹介などから集めた見込み客を、最終的に成約や申し込みに導くための受け皿として機能させる必要があります。
また、SNSでファンを育ててから訪れるホームページと、広告から直接流入してくるホームページでは、求められる構成や情報量が異なります。
つまり、ホームページの内容や設計は「集客の入り口」に応じてカスタマイズすべきであり、これを考えずに制作すると、せっかくの投資が無駄になってしまうのです。
デザインと集客の関係性
ホームページ制作において、デザインに多額の予算を割くべきケースと、そうでないケースがあります。
高級ブランドや世界観を重視する事業(フォトスタジオ、デザイン事務所、高級ホテルなど)では、洗練されたデザインが顧客の期待値と一致するため、投資価値があります。
一方で、機能や価格、実績で勝負する事業では、過剰なデザイン投資は集客効果に直結しません。むしろ、その予算を広告やSEO、コンテンツ制作に回したほうが費用対効果は高い場合が多いのです。
美しいデザインだけでは集客はできず、「自分に役立つ」「悩みを解決してくれる」と見込み客が感じられる情報提供こそが重要です。
ホームページ活用のためのリソース配分
ホームページを活用するには、「時間」か「お金」いずれかのリソースが必須です。
時間がある場合は、ブログ更新やSNS連動、動画制作などでアクセスを集めることができます。時間が取れない場合は、広告運用に予算を投じて流入を確保する必要があります。
作って終わりではなく、公開後の運用計画がなければ、どれほど立派なホームページでも成果は出ません。
例えば、ブログをナビゲーションに設置しているのに更新が1記事だけでは、かえって信頼を損ないます。更新や発信が継続できる体制を整えることが、ホームページ集客の前提条件です。
採用活動におけるホームページの役割
ホームページは集客だけでなく、採用活動においても重要な役割を果たします。求職者は面接前に必ず会社のホームページをチェックし、社風や事業内容を判断します。
ただし、採用応募を増やすためには、ホームページの見た目よりも、実際の職場環境や企業文化の方が重要です。デザインを磨くより、オフィスや設備を整えるほうが、入社後の満足度にもつながります。
また、写真や動画で職場の雰囲気を伝えることは、SNSでは断片的になりがちな情報を体系的に届けるうえで効果的です。
世界観が重要な業種におけるホームページの価値
業種によっては、ホームページが「世界観を伝えるメディア」として不可欠です。
フォトスタジオ、インテリアショップ、アートギャラリー、高級レストランなど、空間や体験そのものが商品価値である場合、SNS発信と併せて、統一感あるデザインと構成でブランドの世界観を表現することが求められます。
実際のサービス体験とホームページの印象が一致しないと、顧客の期待を裏切る結果にもなりかねません。
特に高単価サービスでは、見込み客が比較検討する段階で、ホームページが信頼獲得の決め手になることが多いのです。
ホームページ制作の正しい判断基準
ホームページを作るべきか、作らないべきかを判断するには、まず「自社の集客プロセス」における役割を明確にします。
SNSだけで顧客獲得が可能な業種なら、あえてホームページに投資せず、SNS運用や広告に予算を集中させるのも戦略です。
逆に、信用性や情報の体系化が求められる場合は、必要最低限のデザイン性と機能性を備えたホームページを用意し、その後の運用計画とセットで制作を進めます。
費用のかけ方も、業種・ブランド戦略・集客導線によって大きく変わるため、「とりあえず作る」ではなく「戦略の中で作る」が成功の鍵です。
まとめ:ホームページは戦略の一部として活用する
SNS全盛時代においても、ホームページは業種や事業戦略によっては依然として強力な武器です。しかし、それは単体で機能するものではなく、集客や採用といった目的に合わせて設計・運用する必要があります。
過剰なデザイン投資や「作れば集客できる」という思い込みは危険であり、制作後のアクセス獲得施策が成果を左右します。
自社にとってのホームページの役割を明確にし、現実的なリソース配分と連動させることで、SNS時代でも成果を出せるホームページ運用が可能になります。